 布施南谷にある大山神社(布施南谷林道から入ってすぐです) 今の神木は二代目といわれています。この巨杉も数百年年以上かと・・ |
 大山神社 |
 布施の山祭りのパネル(布施大山神社) 布施こころ公園の宝物館の並河氏撮影のを記載 |
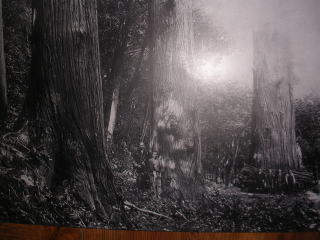 布施南谷の大山神社(大正4年の火災まではこの 大杉が大山神社のご神体として祭られていた。 (樹齢も千年以上と・)この写真も布施こころ公園の宝物館より |
日本最古の巨木信仰の祭りが現存!(布施の岩山哲川氏の言葉)
布施の山祭りは四月の初丑の日です!
布施の山祭りと大山神社
平成22年は4月 3日(土)帯裁(おびたち)の神事 4月4日(日)に帯締めの神事が執り行われます。
布施の山伏マラニックコースのスタートして約1.5k地点・南谷林道に入り右手に大山神社があります。
そこで布施の山祭りが行われます。
 布施南谷にある大山神社(布施南谷林道から入ってすぐです) 今の神木は二代目といわれています。この巨杉も数百年年以上かと・・ |
 大山神社 |
 布施の山祭りのパネル(布施大山神社) 布施こころ公園の宝物館の並河氏撮影のを記載 |
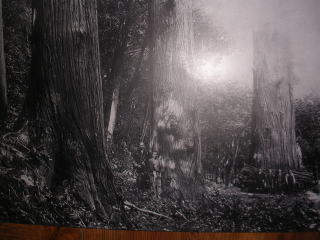 布施南谷の大山神社(大正4年の火災まではこの 大杉が大山神社のご神体として祭られていた。 (樹齢も千年以上と・)この写真も布施こころ公園の宝物館より |
★布施出身の岩山哲川氏から・・・
四月の初丑の日、大山神社のご神木にかずらを巻く。富村安全、五穀豊穣、魔障退散祈念の帯締めの祭りがある。
この大祭昔より記録が無い。おそらく太古からの祭りであろう。
★隠岐の文化材第17号 布施の山祭り解説・・灘部周作氏より
毎年四月の初子の日と翌丑の日(以前は旧暦の二月)の二日間にわたり、大山神社祭礼が行われる。
布施地区では、大山さん、山祭りと呼ばれる神事で、春の到来を実感する行事でもある。
神社といっても社殿は無く、樹齢数百年の老杉を社殿、御神体として祀っている。
四月初子の日を『帯裁ち』と称し、地区の若者15、6名が『帯裁ち人』となって山に入り、大山神事の際、
神木に巻き付けるカヅラ(葛)・ツルを伐る。また『ハナ榊迎え』と称し大山の神霊を『祭り宿』へと迎える際、
神霊の依代となる榊の木を一本とシキミの小木を40本余り伐る。
この大榊を夕刻『祭り宿』へと持ち帰り、来春までの一年間、祭り宿の庭に指し立てておき、
大山神の神宿であることを示すのである。
翌、丑の日は『帯締め』となる。前日山より伐り出した帯(カヅラ)を、『帯締め人』となった若者が木遣り歌に
合わせて、神木の前で激しく揺さぶりながら、神木に七回り半巻き締める。
現在に至るまで、水田の耕作が行われなかった布施は、麦、ソバ、粟などの食物の全てを、奥山を開墾しての
牧畑耕作に頼らざるを得ず、耕作に最も必要な水の精霊である龍神及び隠岐国鎮護の神霊座ます
大山(摩尼山)の遥拝所として、南ノ谷の老杉に大山神の神霊を勧請し、村方繁栄、五穀豊穣、火災不来を祈った。
村の古老は言う、『大山さんは大事な神さんだ』と。この一言が、数百年にわたり大山祭礼を継承し続けた
先人達の大山に対する真摯な念の深さを言い表しているのではないだろうか。
(また、明治期以前の大山祭礼は、村内に移住の法印山伏によって行われていた。)
★竹谷素信氏著・布施の山伏から・・・
大山神社は山神であり、水神も兼ね、神体は神木であるが、山そのものが神体だと考えられている。
祭日は今は四月の初丑で・・改暦以前は旧二月初丑・・の日で、春の山開きを意味していた。
1825年に【大山祭礼記録】が布施の里山伏法印によって書き写されている。・・快教法印
『灘部氏もボロボロになっていた大山神社等の記録を快教法印が書き写したと、
ただそれ以前の大山神社の創建・由来などは調べる事は出来ないと・』更に灘部氏は
『瀬戸内海の愛媛の大三島にあり、全国に11000余りの分社を持つ大山づみ神社が鎮座している
大山づみ神社からの分社かと問い合わせて古文書を調べてもらったが隠岐という言葉は無かったと・・
鳥取の大山(だいせん)とのかかわりは?』
その1825年に書き写された【大山祭礼記録】の最後の方に、この祭礼を始し事、幾百年と云事を・・とある。
この布施の山祭り(祭礼)の起源はいつ頃であったのか、
この記録のできた(1825年)を基にして、「幾百年と云事を・・」と言うのは、百年や二百年では無く、遥か昔かと・・
(中略)
初代神木大杉の樹齢から推せば、1125年頃が適当ではあるまいか。
たとい何れにしてもこの神社は、村民を安堵させるための山伏の企画した祭礼であり、ここが岩座であり、
山伏が霊山に登る途の下の宮でもあったのである。
★たけさん・・
大満寺山(布施山・摩尼山)を囲んでその登山口・有木、東郷にも大山神社が鎮座しています。
隠岐の各地にも沢山の大山神社があります。詳しい言われ等は分りません。又分ればと・・